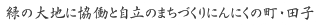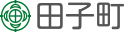福祉サービス・補装具費の支給について
自立支援給付
◇自立支援給付の種類
■介護給付
| サービスの種類 | サービス内容 |
| 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入 浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的 に行います。 |
| 行動支援 | 自己判断力が制限されている人が行動するときに、危険を回避す るために必要な支援、外出支援を行います。 |
| 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包 括的に行います。 |
| 児童デイサービス | 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への 適応訓練等を行います。 |
| 短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期的、夜間も含め施設 で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
| 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上 の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
| 生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等 を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
| 障害者支援施設での夜間ケア等 (施設入所支援) |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等 を行います。 |
■訓練等給付
| サービスの種類 | サービス内容 |
| 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機 能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知 識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労継続支援 (A型=雇用型、B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、 知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助を行 います。 |
◇自立支援給付の利用までの流れ
■相談
受付窓口は、住民課福祉グループです。
↓
■申請
↓
■調査
町の保健師等が家庭等を訪問し、生活や心身の状況等について聴き取りします。
↓
■判定(介護給付の場合)
介護給付の場合、調査の結果をコンピューター及び福祉関係者等からなる審査会で判
定します。
↓
■支給決定
サービス利用者の意向を聴き取りし、福祉サービスの支給決定を行います。
サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を行います。
◇申請に必要なもの
●申請書、世帯状況・収入・資産等申告書
●障害者手帳の写し
●障害年金証書、特別障害者手当、保護開始通知書等の写し(受給している場合)
●医療保険証の写し(被用者保険の場合、同一保険の加入者全員分)
●障害者本人の給料、工賃収入等がある場合は、その収入がわかる書類
●申請者の年金等収入がわかる通帳の写し(申請者が非課税世帯の場合)
●課税証明書
●印鑑
●マイナンバー
■減免申請する場合は以下の書類も必要です
●申請者と生計中心者の通帳残高の写し
●固定資産税納税通知書の明細の写し
(申請者や生計中心者名義の固定資産がある場合)
利用者負担の仕組み
利用者負担は、サービス量と所得に着目した仕組みとなっており、原則1割の定率負担
で所得に応じた月額負担上限額を設定します。また、低所得の方に配慮した軽減策が講じ
られます。
◇月ごとの利用者負担には上限があります
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定され
ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
|
区 分 |
月額負担上限額 | |
| 生活保護 | 0円 | |
| 低所得 | 低所得1 | 0円 |
| 低所得2 | 0円 | |
| 一般1 | 居宅で生活する障害児 | 4,600円 |
| 居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者 | 9,300円 | |
| 一般2 | 37,200円 | |
◇入所施設等を利用する場合の個別減免
入所施設(20歳以上)やグループホーム、ケアホームを利用する場合、低所得1、2
の世帯であって預貯金等が500万円以下であれば、定率負担の個別減免が行われます。
◇同じ世帯で複数人がサービスを利用したとき
同じ世帯のなかで障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービス
を利用する人が介護保険のサービスを利用した場合でも、世帯の月額負担上限額は変わら
ず、これを超えた分が高額障害福祉サービス費として支給されます。
◇食事等実費負担の減免
入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、施設ごとに額が設定されることにな
りますが、低所得の方に対する給付の際には施設における費用の基準を設定し、実費負担
を減免します。
補装具費の支給制度
身体上の障害を補うもので、義手・義足などのように障害者の身体に直接身につけるも
のから、歩行器、車いすなどの費用に対して給付を行います。
◇対象者
●身体障害者手帳を持っている方
◇申請に必要なもの
●補装具費支給申請書
●医師の意見書(初回又は処方に変更があった場合)
●印鑑
◇利用者負担について
補装具費支給制度の利用者負担は、原則として定率(1割)となっています。
ただし、世帯の所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定されています。なお、
世帯に町民税所得割額が50万円以上の人がいる場合は公費負担の対象外となります。
| 区 分 | 世帯収入の状況 | 月額負担上限額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得1 |
市町村民税非課税世帯で、サービスを利用する ご本人の収入が80万円以下の方 |
0円 |
| 低所得2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一 般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |