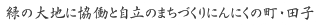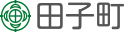マイナンバー制度について
社会保障・税番号(マイナンバー)制度の概要

国の行政機関や都道府県・市区町村間の情報のやり取りをスムーズに進めることで、行政手続きの簡素化、本当に行政サービスを必要としている人をきちんと支援したり、行政の無駄をなくすことを目的に作られた制度です。
- マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
- マイナンバーは、一生使うものです。
※番号が漏洩し、不正に使われる恐れがある場合を除き、一生変更はされません。
マイナンバーの必要性
①役場への提出書類が減る
町民の皆さまが、社会保障・税・災害に関する手続きをする際、役場窓口へ提出する書類がこれまでに比べ少なくなります。
| 社会保障分野 | 年金、雇用保険、健康保険、児童手当、児童扶養手当、障害者手帳など |
| 税分野 | 確定申告書、源泉徴収票、扶養控除、支払調書、法定調書など |
| 災害対策分野 | 被災者生活再建支援金の支給など |
②きめ細やかな行政サービスと不正受給の防止
国の行政機関や都道府県・市区町村などが、所得や行政サービスの受給状況を正確に確認しやすくなるため、本当に行政サービスを必要としている人をきめ細かく支援できるようになります。
また、サービスの不正受給や不当に負担を免れることを防止します。
③行政の効率化
国の行政機関や都道府県・市区町村間の情報のやり取りがスムーズになるため、それぞれの行政機関などで行っている作業の重複などが減り、作業に要する時間や労力が大幅に削減されます。
プライバシーの保護
マイナンバーの漏洩を防ぐため、法律で様々な方法が定められています。
例)・法律で決められた目的以外に、マイナンバーを使用する
・他人のマイナンバーを不正入手する
・他人に不当に提供したりする などを行うと厳しく処罰されます。
また、マイナンバーカードには、所得情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されないため、マイナンバーカード1枚から全ての個人情報が知られてしまうことはありません。
マイナンバーカードについて
- マイナンバーカードの申請、受取
- マイナンバーカード(電子証明書の有効期限)
- マイナンバーカード(継続利用・券面更新)
- マイナンバーカード(暗証番号変更・再設定)
- マイナンバーカード(紛失・返納)
- 顔認証マイナンバーカード
- 国外転出者向けマイナンバーカード
- 個人番号通知書(マイナンバー)
- 公的個人認証サービス
上記内容の詳細については、各ページをご覧ください。
お問い合わせ
制度についてご不明な点がありましたら、下記のコールセンターへお問い合わせください。
◇電話番号
・マイナンバーフリーダイヤル:0120-95-0178
・全国共通ナビダイヤル:0570-20-0178
※ナビダイヤルには通話料が発生します
*一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合、下記の電話番号へおかけください(有料)
・マイナンバー制度に関すること:050-3816-9405
・通知カード、個人番号カードに関すること:050-3818-1250
◎外国語(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)対応フリーダイヤル
・マイナンバーに関すること:0120-0178-26
・通知カード、個人番号カードに関すること:0120-0178-127
※英語以外の言語については平日9時30分~20時までの対応となっています
・外国語窓口全国共通ナビダイヤル:0570-20-0291
※ナビダイヤルには通話料が発生します
◇対応時間
・平日:9時30分~20時
・土日祝日:9時30分~17時30分
(年末年始 12月29日~1月3日を除く)